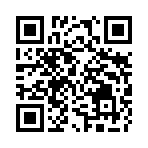http://www.teshima-urara.com/images/banner_obablog.gif
2010年06月25日
研究機関・教育機関としての本質が問われる時代
日本の大学だけでなく、中国の大学でも同じ事を懸念していました。
****************************************************************************************************
改革で見失われた「大学の精神」=定量評価やめ学問的伝統を取り戻せ—復旦大学長(mixiニュースより)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1253271&media_id=31
2010年6月22日、中国青年報は、復旦大学の楊玉良(ヤン・ユーリャン)校長のインタビュー記事を掲載した。中国では大学改革が声高に叫ばれ、世界の一流を目指すという勇ましい言葉が唱えられているが、むしろそうした改革はマイナスだと楊校長は見ており、功利と流行を追い求めるあまり精神的な虚脱に陥っていると厳しく批判した。以下はその抄訳。
楊校長は直接的な利益ばかりを追い求めていることが中国の大学の問題点だと考えている。試験に合格しさえすれば、就職できさえすればいいと考えている教員、学生が多い。専門を選ぶのも興味からではなく、金を稼げるか、出世できるかを考えてのもの。研究者は論文の評価とプロジェクトをクリアすることに奔走し、学問的な出発点を忘れている。もし大学まで汚職にまみれ、性の取引が横行しているのならば、社会の信頼も得られないと楊校長は話した。
虚脱から抜け出し、精神を養うためには、伝統を築き正しい姿に回帰することが必要だという。具体的には、現在流行する個々の研究者や大学を対象とした定量評価をやめなけれえばならないと提言した。かつて米ハーバード大学のロールズ教授は主著『正義論』を完成させることに没頭、15年もの間、一切の論文を発表しなかった。それでも授業には真剣に取り組み、学生たちも尊敬していた。サイテーションインデックス(SCI、被引用数によって論文の評価を決定するシステム)を利用し、個々の論文を点数で評価するシステムで、偉大な研究者を育てることができるだろうかと疑問を投げかけ、復旦大学では海外の研究者に学部評価を委託するなど新たな方法を試していると明かした。(翻訳・編集/KT)
(以上引用)
************************************************************************************************************
■国立大学の教官に任期制の枠があることに数年前驚いたけど,結局すぐに成果の上がる研究や教育ばかりがもて囃され、地道な基礎科学は蔑ろにされたりする嫌~~~な風潮は香川県の国立大学だけではないようです。しかし、希少糖とか直島でヴェロタクシーとか鉄鋼スラグで人工漁礁とか、十年先まで持続できる研究かどうか、非常に疑問です。
★こえび隊などで島々に渡り,作業する大学生はじめ多くの皆様,連日の作業参加御苦労様です。
できればそれぞれの島々で出会った人や文化や民俗や宗教やいきものや豊島の風光を、大学に帰ってから今後の自身の研究に活かして欲しいです。



****************************************************************************************************
改革で見失われた「大学の精神」=定量評価やめ学問的伝統を取り戻せ—復旦大学長(mixiニュースより)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1253271&media_id=31
2010年6月22日、中国青年報は、復旦大学の楊玉良(ヤン・ユーリャン)校長のインタビュー記事を掲載した。中国では大学改革が声高に叫ばれ、世界の一流を目指すという勇ましい言葉が唱えられているが、むしろそうした改革はマイナスだと楊校長は見ており、功利と流行を追い求めるあまり精神的な虚脱に陥っていると厳しく批判した。以下はその抄訳。
楊校長は直接的な利益ばかりを追い求めていることが中国の大学の問題点だと考えている。試験に合格しさえすれば、就職できさえすればいいと考えている教員、学生が多い。専門を選ぶのも興味からではなく、金を稼げるか、出世できるかを考えてのもの。研究者は論文の評価とプロジェクトをクリアすることに奔走し、学問的な出発点を忘れている。もし大学まで汚職にまみれ、性の取引が横行しているのならば、社会の信頼も得られないと楊校長は話した。
虚脱から抜け出し、精神を養うためには、伝統を築き正しい姿に回帰することが必要だという。具体的には、現在流行する個々の研究者や大学を対象とした定量評価をやめなけれえばならないと提言した。かつて米ハーバード大学のロールズ教授は主著『正義論』を完成させることに没頭、15年もの間、一切の論文を発表しなかった。それでも授業には真剣に取り組み、学生たちも尊敬していた。サイテーションインデックス(SCI、被引用数によって論文の評価を決定するシステム)を利用し、個々の論文を点数で評価するシステムで、偉大な研究者を育てることができるだろうかと疑問を投げかけ、復旦大学では海外の研究者に学部評価を委託するなど新たな方法を試していると明かした。(翻訳・編集/KT)
(以上引用)
************************************************************************************************************
■国立大学の教官に任期制の枠があることに数年前驚いたけど,結局すぐに成果の上がる研究や教育ばかりがもて囃され、地道な基礎科学は蔑ろにされたりする嫌~~~な風潮は香川県の国立大学だけではないようです。しかし、希少糖とか直島でヴェロタクシーとか鉄鋼スラグで人工漁礁とか、十年先まで持続できる研究かどうか、非常に疑問です。
★こえび隊などで島々に渡り,作業する大学生はじめ多くの皆様,連日の作業参加御苦労様です。
できればそれぞれの島々で出会った人や文化や民俗や宗教やいきものや豊島の風光を、大学に帰ってから今後の自身の研究に活かして欲しいです。